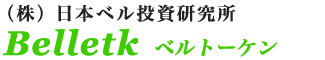投資に活かすコミュニケーション
2025.03.25 (火) 10:03 AM
・<「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか?>という本(日経BP)を読んでみた。著者の今井むつみ氏(慶大教授)は認知科学、言語心理学、発達心理学の研究教育者である。認知科学からみたコミュニケーションのあり方について、どうしたらよいかのヒントが多数得られる。
・まず自らの経験を3つほどあげてみたい。1つは、誤解である。十分会話しているはずなのに、その文脈の中で使った言語や言い方が、感情的に別の印象を与えてしまう。そこだけがインパクトとして残ってしまう。
・相手は別の意味に受け止めて、感情的対立だけが目立ってしまうことがあった。こちらの言い方が悪かったかもしれないが、本音をしゃべっているので嘘はついていない。でも、意味や意図が全く伝わらない。
・2つ目は、自らの意見を表明した時、そもそも改革派に賛成していた。一方で、保守派がなぜ反対しているか。その本音の論理をもっと聞き出すべく、対話を進めようとしたら、その時の言動の一部を切り取って、私は保守派であるというレッテルが貼られた。
・参加していた人の中に、そう受け止める人が出た。曲解であるのだが、それが長く残って、払拭するのが大変であった。一回刷り込まれると、上書きするには時間がかかる。
・3つ目は、経営者のプレゼンテーションを聞いて、その意味を解釈しようとする時、自分が重要と受け止めたことと、他者が受け止めたポイントが大きくずれていることがある。
・毎年参加している世界経営者会議でのプレゼンを聞いた時、その後の新聞の記事を見て、論点はそこではない、と感じたことが何度もある。とすると、新聞記事を読んで、真に受けることはかなり危うい。同じ情報が発信されても、受けての感じ方で、その意味内容がかなり変質するということはいくらでも起こりうる。
・今井先生は、人は自分の都合がいいように誤解する生き物なので、言い方を工夫するとか、言い換えてみるとかでは、分かってもらえないという。何回説明しても伝わらないということが起きる。
・コミュニケーションは、人々の認知力に依存する。認知は、言語、文脈、記憶、想像などに依存し、この認知が働く仕組み(スキーマ)が人によって違っている。頭の中の当たり前が同じではないので、受け止め方は当然違ってくる。
・何らかの思いを、言語で表現しても、その意図は受け手によって、勝手に解釈されてしまう。自分が分かるように受け止めて、それが相手の言いたかったことと理解してしまう。これは、困ったことである。
・人によって、知識や思考の枠組み(スキーマ)が違うのであるから、情報の出し手と受け手で同じように認識するとはいえない。ここを研究していくのが認知心理学である。自分なりの理屈と相手思い込みが対峙してしまう。ここをどう解きほぐして、相互理解を深めていくか。
・私は、経営者の話を聞いた時、自分なりに速記していく。長年の訓練で、話の内容を再現できるようにメモすることができる。それでも、それは私のメモで、相手が話したこと、そのものではない。さらに、その話のポイントは何かと、例えば3つにまとめたとすれば、それは所詮、私のまとめ方であって、相手が伝えたかったことではないかもしてない。
・人の記憶は脆弱で、肝心なことをすぐに忘れても、どうでもよいことは妙に覚えていたりする。相手が話したことを忘れても、こちらは覚えている。あるいは、こちらは話したことを忘れても、相手が覚えている。
・私は常に本音で話し、嘘やカモフラージュ(とりつくろってごまかすこと)は言わないことにしている。そうすると、言ったことは忘れてしまっても、いつも考えていることを言っているので、その考えは場当たりではなく、いい加減なものでもない。但し、本音をいうので、これがその場に合わず、相手に不快感を与えてしまうかもしれない。表現には気をつけるが、いい加減な忖度はしない。
・情報にバイアスはつきものである。二度、三度とバイアスをきかされると、それをホントと思ってしまう‘記憶の強化’がなされる。ここに一番気を付けたい。知りたいことと、伝えたいことには、絶えずギャップがある。人は自分に都合のよい、心地良い情報を好む。そういう情報を聞きたいと思っていると、そういう情報が優先して目や耳に入ってくる。
・嫌な情報は聞きたくないので、当然入ってきにくい。情報のバイアスを、絶えず疑った方がよい。自分の視点ではなく、別の視点として、例えば第三者の視点で、あるいはもう一人の自分に視点でみてみることが重要である。
・世の中には、記憶力の良い人がいる。いわば記憶の天才である。その人の悩みは、忘れないことにある、という話を聞いた。忘れないということは、いいようで辛い。記憶する勉強にはよい。でも、嫌なこと、辛いことは、適度に忘れていくから、人生は生きていけるという面もある。
・普通の人はもっと覚えていたいにも関わらず忘れてしまう。日常の生活でも、記憶はいい加減で、曖昧なことも多い。やはり覚えておきたいことは、メモをしたり、ストーリー仕立てにしたり、人に話したりして、再現できるようにしておきたい。
・自分の情報にもバイアスがある。その情報に自信をもって、判断を決めつけても、実は誤っていることもある。人に誤解を与えてしまうこともある。相手の信頼を失ってしなうかもしれない。こうしたバイアスにはよくよく注意して、思い込みに陥らないように、確認する動作を怠らないようにしたい。
・相手の話をよく聞く。つい自分の話ばかりしてしまうが、半分以上はきくことである。次に相手の立場を理解しようとする。すぐに反論して、相手を否定したくなるが、これは押し付けである。押しつけは人に嫌われる。相手の立場を考えて、話すことが求められる。これは意外に難しい。ストレスがたまるかもしれない。
・人間は感情の動物である。自分が話すことを聞いてもらうとスッキリする。ということは、相手の話も同じように聞いていきたい。聞きながら、その意味するところをよく咀嚼していく。
・受け止めるだけでなく、どういうことか、どうしたいのか、などと思いをめぐらす。その上で自分の意見を言うのではなく、さらに相手の話を聞き出していく。この「話させ上手」が極めて大事である。これがうまくいくと互いに楽しくなる。
・そうすると、互いに分かったという内容が出てくる。腹落ちすることがあると、コミュニケーションがうまくいったと感じる。答えはないかもしれないが、悩みは共有できる。あるいは、答えが出て、次のアクションがみえてくるかもしれない。こうなったら共感が生まれてこよう。
・私としては、「メタ認知」を大事にしたい。自分が持っている認知のスキーマ(仕組み)をもう一段別の視点から見直すことである。これによって、自らの意思決定の客観性を高めることができる、という今井先生の指摘を実践したいと思う。楽しいコミュニケーションをぜひ投資に活かしたい。