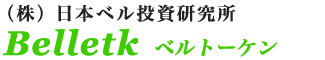人材はいるか
2025.04.08 (火) 5:34 PM
・企業を評価する時、どこをみるのか。事業の成長性、業績の数値、経営者の資質、企業の風土などさまざまな視点があろう。投資家としては、株主になった場合を想定して、自分の視点をしっかり定めておくことが大事である。そして、その視点をブレないで継続することである。
・企業には、環境変化に付随してさまざまな事案が発生する。変化というのは良いことも悪いことも含むが、事案となると想定外の問題が発生して、会社にネガティブな影響をもたらす。その時、どうするか。
・準備が出来ていれば、想定外ではない。突然の事案であっても、次の打つ手が見えるようであれば、何とかなる。先が見通せず、時間を要する場合は、緊急対策と中長期の対策を分けて進める必要がある。
・平時と有事の場合で、リーダーに求められる資質は異なる。有事に強い経営者かどうかは、どうやって見分けられるのか。何よりも説明責任を果たすことができるかをみていく必要がある。
・次に、結果責任の取り方が問われる。責任をとってやめればよいというものではない。次の手を打って、事態を打開していくことをどこまでリードできるか。その行動力を見極めたい。
・企業のオペレーションは、通常、いつものように恙なく進められて当たり前である。各々の社員が、分担に応じて自らのタスクを実行していく。これが順調であれば、一定の成果が予定通り出てこよう。ピッチが揃うと計画を上回る成果を生み出すことも多い。これは大いにポジティブである。
・ところが、日々、どこかに小さなインジデント(事案)が起きている。それでも、現場で手が打たれて、特に大事に至らずカバーされていることも多い。リスクマネジメントが機能し、事態がコントロールされているので、外部からは何も目立たない。一次的な揺れが大きくても、それがコントロールされるのであれば、その企業のリスクマネジメント力は高いといえよう。
・そういう組織をどのように作っていくか。人材の採用、育成、働き方のインセンティブが問われる。大きな企業になると、人事部門が重要な役割を果たす。CHROのプロとしてリーダーシップがカギとなる。
・誰でも一人でできることは限られている。チームとして、組織として、ミッションを遂行し、目標の達成を目指す。それでも、1人ひとりのジョブとスキルが自他ともに分かって、それを発揮しつつ、さらに向上することが業務プロセスに組み込まれているか。
・ジョブを担うキャリア開発と、その技量を育てるスキル開発が両輪であり、その開発に自分が乗っているとなれば、やる気も一段と高まってこよう。
・スキル開発、キャリア開発には、異質な体験が重要である。いつもの仕事は、いつものようにこなして当たり前である。その日常的な働き方は大事であるが、レベルアップには新しい体験が必要である。
・異質な社会体験、これまでと違った組織での働き、全く新しいスキルを身に付ける学習などが大いなる刺激となろう。こうした人材開発が社内全体のどこまで浸透しているのか。1)限られた人材の育成にとどまっているのか、2)全社員に広がっているのか、3)各層のレベルによって的確になされているか、ということを知りたい。
・人材の出入りも重要である。足らない人材は外部から、余剰な人材は外部へ、という新陳代謝も活力の維持には必要である。多くの中堅企業では、足らない経営幹部を外部から採用できず、一方で、次の見込みのある若手を社内に留めることができずに出ていってしまう、ということが起きている。これでは、その会社の将来が危うい。
・トップインタビューをしていると、社長が人材育成にどこまで熱心かというのが比較的よく伝わってくる。熱心でない社長は、社内の人材に不満をもっている。熱心な社長は、若手のこともよく知っており、同業他社の経営人材とも交流が深い。
・日本IBMでは、人材開発に当たって、2つのプラットフォーム(PF)をもっている。キャリア開発の「your carrier」とスキル開発の「your learning」である。専門アドバイザーによる丁寧なヒューマンサポートと同時に、AIを活用したデジタルサポートにも大いに力を入れている。未病、育児、介護にも目配せしている。
・働く社員からすると、1人ひとりの個人をどれだけ大切にしてくれるか。企業の組織からみると、全社員を対象とした組織的人的資本の良さが問われる。ここがパワーを発揮してくれば、生産性が一段と上がってこよう。新しい価値を生み出す源泉となる。
・ここを、わが社独自の指標として開示してほしい。育成の仕組み、現場での活躍、次の経営人材の登用などに、特に関心がある。人的資本の目にみえない資産が、価値創造にいかに貢献しているか。ここの見える化に期待したい。
・最後は、CEOの力量にかかっている。今のCEOに一定の限界がある時、次は誰になるのか。次の候補者は、本当に実力はあるのか。その選び方、選ばれ方、これまでの実績からみた実力を見極めて投資に活かしていきたい。