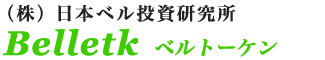サイバー戦に負けないために
2025.04.14 (月) 3:27 PM
・いろんな情報が入ってくる。私のメールには、メルアド(メールアドレス)が確認できないと、SPAMという表示がつく。迷惑メールの可能性があるので、うかつに開かない。返信しないことにしている。身元をよく確認してから対処する。
・なりすましサイトも多い。かなり巧妙になっている。確認して返信したくなるような内容となっているが、一切無視している。本当に問題があったら、もっと個別具体的に連絡がくるはずである。それでも思い当たることがない場合は相手にしない。それで困ったことは一度もない。
・インターネット社会は誠に便利で、その恩恵をフルに受けているが、欠点や限界も目立っている。次なるイノベーションで、現在の課題を克服してほしい。そうなれば当然次に課題が生まれてくる。社会の発展につきもので、追い駆けっこであろう。
・ネット上には偽情報(disinformation)が溢れている。何が本当で何が嘘か、それを見分けるのは簡単ではない。シンプルなファクトなら、辞書やデータ集で確認できるが、何らかの解釈、意図、主義主張などが入ってくると、その立証は難しくなる。
・世の中の大半の情報は嘘だと思った方がよい。そこからスタートしたい、という意味である。どんな情報も一面的であり表面的であって、深堀してみると、違った側面を多々含んでいる。
・ただ、受け手としては、すべての情報にいちいち反応しているわけにはいかない。自分にとって、身近で関心がある情報については、注意深くフォローして、当然理解を進めていく。
そうすると、関心ある情報について“自分にとっての良し悪し”がわかってくる。悪しき情報も目立ってくる。
・ということは、自分が関心のない、よく知らないことについての情報も似たようなレベルにあるということである。その情報にも良し悪しがある。よって、だまされないようにまず距離をおきたい。
・自分が知っていること、関心があることにも注意したい。自分にとって心地よい情報は鵜呑みにしやすい。確信を高めるような追加情報がくると、やはりそうかと納得してしまう。
・これまでの思い込みが強いと、その考えを修正することに柔軟でなくなり、他の情報を拒否するようになる。意見の合わない人と議論できなくなり、会うこともきらいになる。同質の人たちだけで固まって、偏屈になりかねない。
・サイバー攻撃はここを攻めてくる。単なる偽情報ではなく、もう少し工夫をして量で攻めてくる。社会の矛盾を分かり易くみせて、その亀裂を深くするような情報を出してくる。人々の判断をゆがめて、社会に混乱を起こすことを狙っている。世界をみれば、選挙に介入したり、貧困、移民、人権について一方的な情報を流したりして、相手を攻撃していく。
・「安全保障分野におけるサイバー戦」について、自衛隊の廣惠陸将の講演を聞く機会があった。ウクライナのサイバー戦では、1)兵や家族を対象にした心理戦、2)位置特定や攻撃指揮で連携する情報錯乱戦が実行されている。
・わが国の自衛隊も、伝統的な陸・海・空から、電磁波・宇宙・サイバー領域へ、さらに
認知領域へと防衛のワクを広げている。認知戦とはナラティブ(言語によるストーリー)によって、人々の認知(脳の知的受け止め)に影響を与え、自らに有利な状況を作り出す作戦のことをいう。
・3月に、笹川・読売グローバルフォーラム「偽情報といかに戦うか」が開催された。その内容が参考になる。地政学的リスクが高まる中で、言語によるサイバー攻撃がまさに武器・弾薬になる。
・ハイブリッド戦争なので、ハードとソフト、武力とサイバー、情報戦と認知戦、ネットワークの破壊と頭の中の洗脳の戦いといえよう。偽情報をいかに作って、うまく流すか。良いいも悪いもない。嘘を作り出して、それで人々をいかにも洗脳し、相手の社会を分断し、混乱させていく。
・H.マクマスター氏(第1次トランプ政権の国家安全保障担当大統領補佐官)は、ロシアの3D作戦、中国の3C作戦にいかに対抗し、防衛するかについて語った。
・ロシアは、①disrupt~社会を混乱させ、②dependency~自国のエネルギーに依存させ、③deny~侵略行為を徹底的に否定する、という作戦をとっている。偽情報によるプロパガンダ(世論を誘導する宣伝)、認知戦による怒りや不満の植え付けによって、最後は政府のクーデター(転覆)にもっていくというやり方である。
・中国は、①co-option~異なる考えの分派吸収、②coercion(威圧による弾圧)、③concealment(故意に隠す隠蔽)を遂行する。台湾国民を自らの方に招き入れる。そのために、買収や破壊活動を支援する。台湾が自国の防衛を減らすように仕向け、米国の台湾防衛をあきらめさせようとする。
・これを北村氏(元国家安全保障局長)は、「三戦の攻め」という。①法律戦、②世論戦、③心理戦である。孫子の兵法(戦わずして勝つ)の利用ともいえる。
・日本はどうか。2022年の経済安全保障推進法で、サイバー攻撃への備えを一歩進めた。わが国の基幹インフラ14業種に対して、コンピューターシステムなどの重要設備導入時に事前審査を行うようにした。
・また、2025年の今国会では「能動的サイバー防衛」を法制化しようとしている。これは平時からネット空間の通信を監視し、国の重要インフラに対するサイバー攻撃への予兆を発見し、先手を打つことができるようにする。
・専守防衛において、従来型の防衛力に加えて、サイバー領域、認知領域を充実させていく。これは不可欠であり、かなり急ぐ必要がある。サイバービジネスはグローバルに大きく成長しよう。
・認知領域のサイバー戦は、国防でも、民防でも一段と重要性を増している。情報量で稼ぐ仕組みは見直されてしかるべきである。情報の質、情報の価値に対して、対価を支払う新しいビジネスモデルの構築が求められよう。
・閲覧数(インプレッション数)で稼ぐ広告モデルはまやかしの情報で人目を引けばよいという風潮を助長させる。これを上書きするビジネスモデルの登場に期待しつつ、サイバー戦に強い企業に投資したい。